高齢者はなぜこんなに寒がりになるの?
その理由と、具体的な対策を知りたい方へ。
この記事では「高齢者の寒がり 対策」にフォーカスし、室温や湿度の適正値から、断熱・気密、暖房器具の選び方、衣類や生活習慣まで、今すぐ取り入れられる6つの実践ポイントをわかりやすく紹介します。
結論から言うと、ちょっとした工夫と習慣の見直しで、室内はぐんと暖かくなります。寒がりでお困りの方やご家族は、ぜひチェックしてみてください。
なぜ高齢者は寒がりになりやすいのか?その原因を解説
年齢とともに筋肉量や代謝、自律神経の働きが低下し、体温をうまく保てなくなることが高齢者の寒がりの主な原因です。
筋肉量の減少で体温を維持しにくくなるから
加齢によって筋肉量が減ると、体が熱を作り出す力も低下します。
筋肉は体温を維持するエンジンのような存在なので、運動不足も重なって冷えを感じやすくなるのです。
血流が悪くなりやすく冷えを感じやすいから
血液の流れがスムーズでないと、手足の末端にまで温かさが届きません。
年齢を重ねると血管が硬くなりがちで、結果的に手足が冷えやすくなります。
皮膚の感覚が鈍くなり寒さに過敏になるから
高齢になると皮膚の感覚が鈍くなり、ちょっとした温度変化にも敏感になります。
体が実際以上に寒さを感じることで、余計に寒がりに拍車がかかります。
代謝の低下で体が熱を作りにくくなるから
代謝が落ちると、体が内側から熱を生み出す力も低下します。
食事量の減少や活動量の減少が原因となり、ますます寒さを感じやすくなるのです。
自律神経の働きが衰えて体温調整が難しくなるから
自律神経は体温をコントロールしていますが、年齢とともにその調整機能も低下します。
外気温に対して適切に対応できず、寒暖差に弱くなってしまうのです。
寒がりな高齢者に最適な室内の温度と湿度とは
快適な室温・湿度を保つことで、体への負担を減らしながら暖かさを維持できます。適切な湿度管理も体感温度を高める鍵になります。
室温は20〜22度を目安に保つこと
高齢者が快適に過ごすためには、室温は20〜22度が基本的な目安とされています。
ただし寒がりの方は22度以上に設定しても問題ありません。
エアコンやヒーターをうまく活用し、朝晩の冷え込みや日中の寒暖差にも柔軟に対応しましょう。
また、エアコンだけでなく、こたつやホットカーペットなどと併用すると、より効率的に暖かさを保てます。
湿度は40〜60%が快適な環境とされていること
湿度が低すぎると体感温度が下がり、同じ室温でも寒く感じてしまいます。
一方、湿度が適切であれば、空気の保温性が高まり、暖かく感じられます。
加湿器のほかにも、洗濯物の部屋干しや濡れタオルを使った自然加湿も効果的です。
湿度を意識することで、風邪予防や乾燥対策にもつながります。
部屋ごとの温度差を少なくすること
家の中で部屋ごとに温度が違いすぎると、寒暖差によって体に負担がかかります。
特にトイレや浴室などでの急激な温度変化は、ヒートショックの原因にもなります。
廊下や脱衣所にも暖房器具を設置したり、扉を開けたままにして空気を循環させたりするなど、部屋ごとの温度差をできるだけ少なくする工夫が重要です。
加湿器を使って乾燥を防ぐこと
暖房を長時間使うと空気が乾燥し、喉の痛みや肌トラブルの原因になります。
加湿器を併用することで、室内の湿度を保ち、体感温度を上げるだけでなく、ウイルス対策にもつながります。
最近ではアロマ機能付きの加湿器もあり、リラックス効果も期待できます。
温湿度計を使ってこまめにチェックすること
目で見てわかる数値があると、適切なタイミングでの調整がしやすくなります。
体感だけでは気づきにくい変化も、温湿度計があればすぐに把握できます。
手の届く場所に設置して、日々の習慣としてチェックすることが寒がり対策の第一歩になります。
断熱・気密で変わる!室内を暖かく保つ住宅の工夫
住まいの断熱・気密性を高めることで、熱の出入りを抑え、冷気の侵入を防ぎます。部屋ごとの寒暖差も軽減できて安心です。
窓に断熱シートやカーテンを使って冷気を遮断する
冷気の多くは窓から侵入します。特にガラス面は外気の影響を受けやすく、室温を一気に下げてしまう原因になります。
断熱シートを貼ることで熱の移動を防ぎ、厚手のカーテンを使えば保温性もさらにアップします。
さらに、カーテンボックスを設置したり、床まで届く長さのカーテンにすることで、下からの冷気の侵入も防ぐことができます。
床にカーペットやマットを敷いて底冷えを防ぐ
フローリングの床は思っている以上に冷たく、足元から体全体を冷やしてしまいます。
保温性の高いマットや厚みのあるカーペットを敷くだけで、足元の冷たさが大幅に軽減されます。
断熱素材のラグやホットカーペットと組み合わせることで、より暖かく快適な空間を実現できます。
すきま風を防ぐためにドア下や窓枠の隙間を塞ぐ
目には見えにくいけれど、ドアや窓のわずかな隙間からも冷たい風が入り込んでいます。
すきまテープやモール、パッキンを使ってしっかりと塞ぐことで、冷気の侵入を防ぎ、室温の安定につながります。特に玄関や北側の部屋は要注意です。
内窓を設置して二重サッシ化する
断熱性を飛躍的に高めたい場合は、内窓を追加して二重サッシにするのがおすすめです。
既存の窓枠にもう一枚窓を取り付けるだけで、外気の影響を大幅に遮断できます。
結露の軽減や防音効果も期待できるため、寒さ対策以外にもメリットが多い方法です。
壁や天井の断熱材を強化する
築年数の古い住宅では、壁や天井の断熱材が不十分なことがよくあります。
断熱材の追加やリフォームによって室内の保温効果は格段に向上します。
費用はかかりますが、長期的に見れば暖房費の削減にもつながり、快適な住環境が手に入ります。
玄関や浴室の断熱対策も忘れずに行う
家の中でも特に冷えやすい場所が玄関と浴室です。玄関には厚手のカーテンや隙間ふさぎテープ、
浴室には浴室用の断熱パネルやマットを設置すると効果的です。
温度差の激しい場所だからこそ、入念な対策が必要です。
電気代を抑えながら暖かさを保つ暖房器具の選び方
暖房器具の性能や使い方を工夫すれば、電気代を抑えつつ、効率的に室内を暖かく保つことができます。選び方のコツを紹介します。
エアコンは省エネ性能の高いモデルを選ぶこと
最新の省エネモデルにすることで、暖房の効率が上がり電気代の節約にもつながります。
特に「省エネ基準達成率」の高い製品や、スマート機能で細かく温度管理ができるモデルは、使用頻度の高い冬場にこそ力を発揮します。
また、フィルターの掃除をこまめに行うことで効率が維持され、省エネ効果もさらにアップします。
こたつや電気毛布などスポット暖房を活用すること
部屋全体を温めるよりも、体の周辺だけを集中的に温めるスポット暖房は、エネルギー効率が高く経済的です。
こたつは足元をしっかり温めてくれますし、電気毛布は布団の中に熱を閉じ込めてくれるため、就寝時にぴったり。
電気座布団やハンドウォーマーなども併用すると、さらに効果的です。
オイルヒーターは空気を乾燥させにくく安全性が高い
オイルヒーターは燃焼がないため、空気を汚さず乾燥もしにくい特徴があります。
火を使わないので高齢者が使用する際にも安心で、安全性を重視する方に向いています。
じんわりと室内を均一に暖めるため、急激な温度変化が少なく、体への負担も少ないのが魅力です。
サーキュレーターで暖気を循環させること
エアコンやヒーターの暖気は天井にたまりがちなので、サーキュレーターを使って空気を下へと循環させると、室温のムラが解消されます。
上下左右に首振りできるタイプを選べば、部屋全体の空気をバランスよく混ぜられ、より効率的に暖かさを保つことができます。
加湿器と併用すれば、乾燥対策にもなります。
タイマー機能で無駄な電力消費を防ぐこと
暖房器具を使う際、つけっぱなしは電気代の無駄につながります。
タイマー機能や人感センサー付きの製品を活用することで、必要なときだけ稼働させられ、節電になります。
特に就寝時や外出時の消し忘れ防止にも効果的で、安全面でも安心です。
寒さ対策に効果的な衣類や寝具の活用法
暖かさを保つには、衣類や寝具の工夫も欠かせません。軽くて保温性の高い素材や小物を活用して、快適に過ごす方法を解説します。
発熱素材のインナーを活用する
ヒートテックなどの発熱素材のインナーは、薄手でもしっかり暖かく快適です。
特に肌に直接触れるアイテムは、熱を効率よく閉じ込めることで、外出時の寒さや室内での冷え対策に役立ちます。
また、吸湿発熱タイプは汗を吸って発熱するため、冬場でも汗をかきやすい方にぴったりです。
重ね着で空気の層を作り保温効果を高める
服を何枚か重ねることで、間にできる空気の層が断熱材のような役割を果たします。
インナー、中間着、アウターといった順で重ね着をすることで、効果的に体温をキープできます。
特に室内外を出入りする場合は、脱ぎ着がしやすい構成にすることがポイントです。
フリースやダウンなど軽くて暖かい素材を選ぶ
高齢者には、重くないけどしっかり保温してくれる衣類がぴったり。動きやすさも重視しましょう。
フリースは軽くて速乾性があり、室内着にも最適ですし、ダウンジャケットは外出時の冷気をしっかり遮断してくれます。
素材選び一つで暖かさが大きく変わります。
寝具には電気毛布や湯たんぽを取り入れる
寝ている間に体が冷えると睡眠の質も低下。電気毛布や湯たんぽで就寝前から布団を暖めておくのがおすすめです。
電気代が気になる場合は、湯たんぽを活用すると省エネにもなります。
カバー付きのものを選ぶと火傷の心配もなく安心して使えます。
首・手首・足首をしっかり保温する
「首」と名のつく部位は冷えやすく、保温すれば体全体の暖かさをキープしやすくなります。
ネックウォーマーやレッグウォーマー、リストバンドなどの小物を取り入れることで、外出時だけでなく室内でも簡単に冷えを防ぐことができます。
高齢者の寒がり対策として取り入れたい生活習慣
運動や食事、入浴など、日々の生活習慣の見直しによって体を内側から温めることができます。簡単に取り入れられる習慣をご紹介。
毎日の軽い運動で筋肉量と血行を保つこと
散歩やラジオ体操など、無理のない範囲で体を動かすことで冷えにくい体づくりができます。
特に朝に軽い運動を行うことで、一日の体温が安定しやすくなり、血流の改善にもつながります。
テレビを見ながらの足踏み運動やイスに座ってできる体操など、生活に取り入れやすい工夫もおすすめです。
バランスの良い食事で代謝を上げること
栄養バランスの取れた食事は体の中からエネルギーを生み出します。
特にたんぱく質やビタミン類を意識して取りましょう。根菜類や温かいスープなど、体を内側から温めてくれる食材を積極的に取り入れるのも効果的です。
1日3食をしっかり摂ることも基本になります。
温かい飲み物で内側から体を温めること
白湯や生姜湯など、体を冷やさない飲み物をこまめにとることも立派な冷え対策です。
とくに寒い朝や夜は、温かいお茶やノンカフェインのハーブティーなどでリラックスしながら体を温める習慣をつけましょう。
甘酒やみそ汁などもおすすめです。
入浴はぬるめのお湯で長めに浸かること
熱すぎるお湯は逆効果。ぬるめのお湯にじっくり浸かることで、体の芯から温まりやすくなります。
目安としては38〜40度のお湯に10〜15分程度。
お気に入りの入浴剤を使えば、血行促進やリラックス効果も得られ、心身ともにポカポカになります。
冷えやすい時間帯には厚着を心がけること
朝晩は気温が下がるので、時間帯に応じた服装の工夫をすることが大切です。
外出時だけでなく、室内でも体温に合わせてカーディガンやひざ掛けを活用するなど、細かな調整が冷えを防ぎます。
タイマー付き暖房機器の活用も有効です。
寝る前にストレッチや足湯を取り入れること
寝る前に体をほぐすことで血流が良くなり、布団に入ってからも冷えを感じにくくなります。
簡単なストレッチや、洗面器を使った足湯を10分ほど行うだけでも効果的。
リラックス効果も高まり、ぐっすり眠れるようになるでしょう。
高齢者の寒がり対策についてまとめ
高齢者の寒がりは、体の変化によるもので誰にでも起こり得る自然な現象です。
ですが、日常のちょっとした工夫で快適に過ごすことは十分に可能です。
この記事では、室温・湿度管理、住宅の断熱、電気代を抑える暖房器具の使い方、衣類・寝具の工夫、そして毎日の生活習慣まで、6つの実践的なポイントを紹介しました。
寒さに悩むご本人も、ご家族も、今日から始められる対策ばかりです。暖かく安心して過ごせる室内環境づくりに、ぜひ役立ててください。
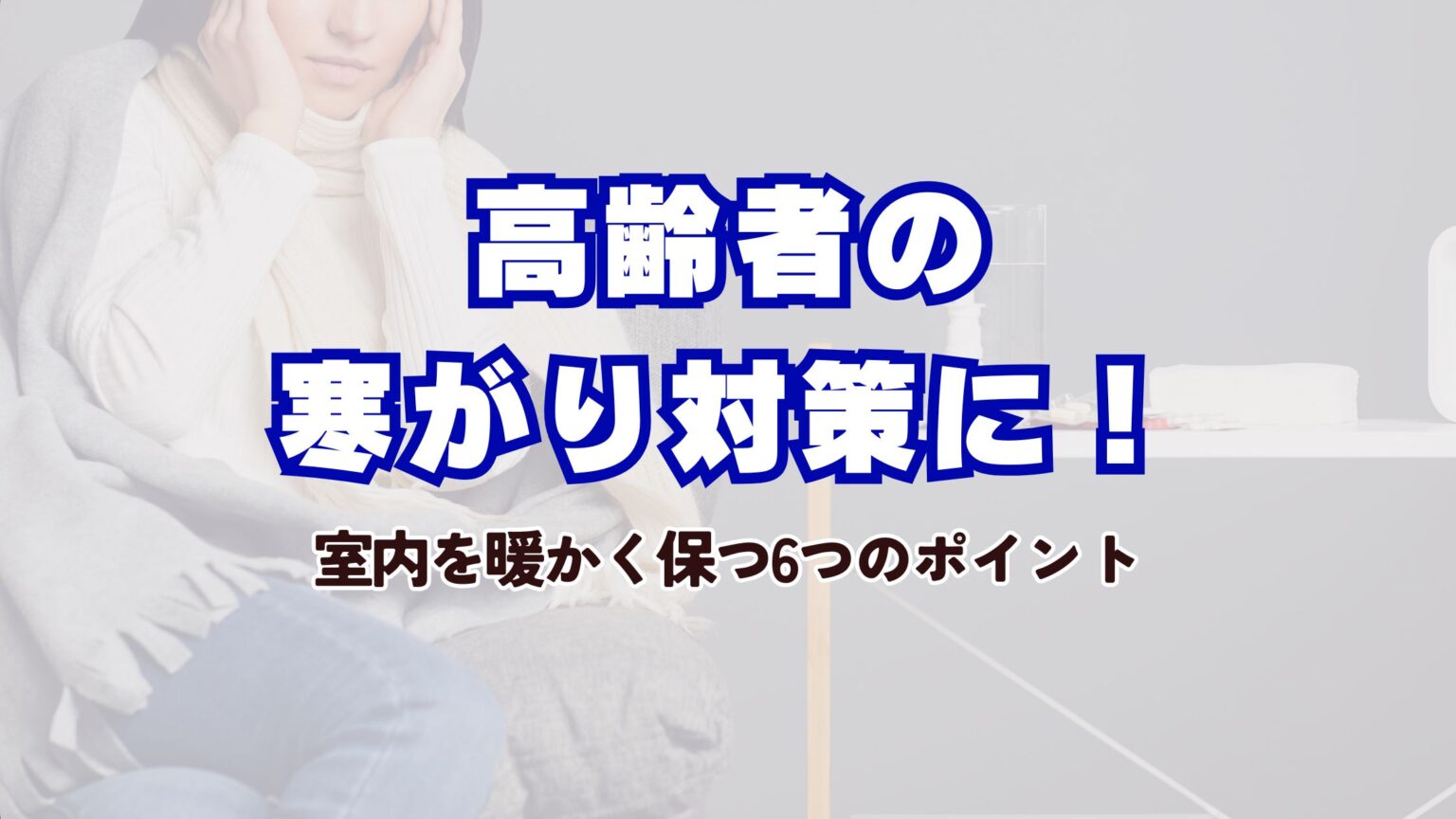
-120x68.jpeg)
